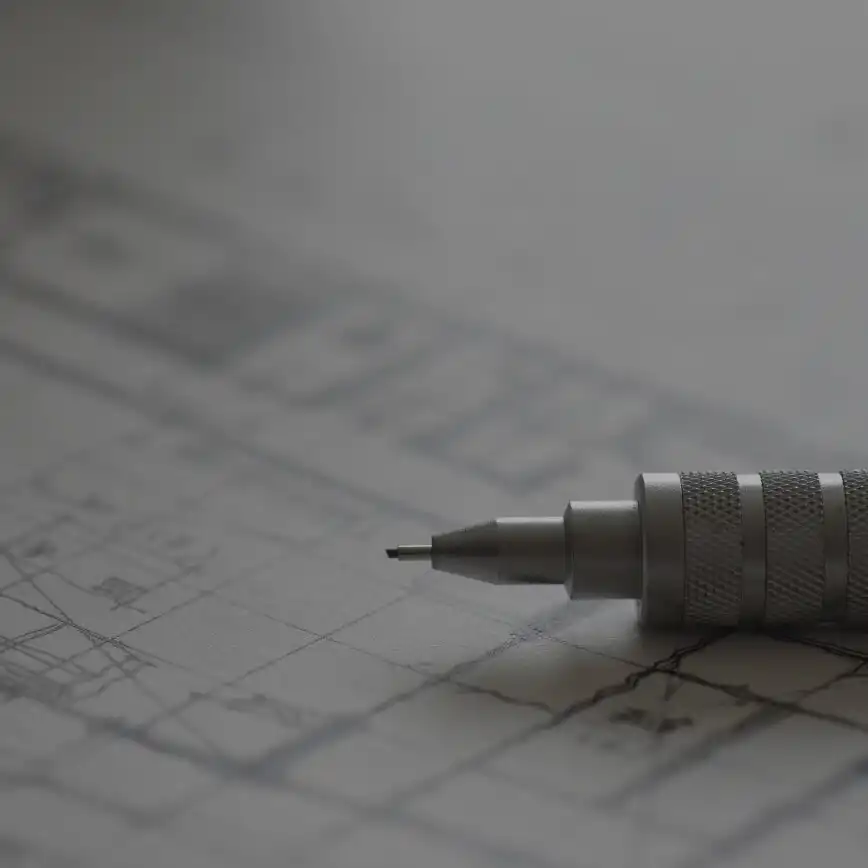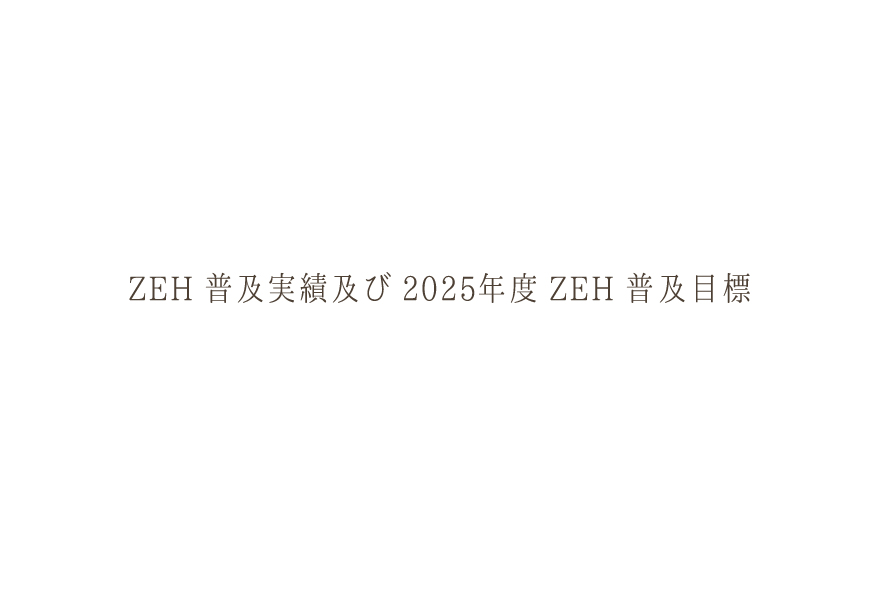こころときめく。
くらしはなやぐ。
ドアを開けるたびに、こころがはずむ。
なんでもない日々が、あざやかに彩られる。
その空間のここちよさには、理由があります。
長い時間を過ごす場所だからこそ、
その時間がよりゆたかになるように。
アップルハウスは、
あなたの理想と未来によりそいます。





01
お客様に寄りそう
家づくり
ライフスタイル、仕事、趣味、かなえたい夢。
人それぞれの「かたち」があるからこそ、
一人ひとりに寄りそった家づくりを
お約束します。
02
早く帰りたくなる、
デザイン性の高い住まい
住まいは、ご家族の生活を彩る器だから。
外見も内装も、思わずワクワクするような
デザイン性の高い家づくりが、
アップルハウスの得意分野です。





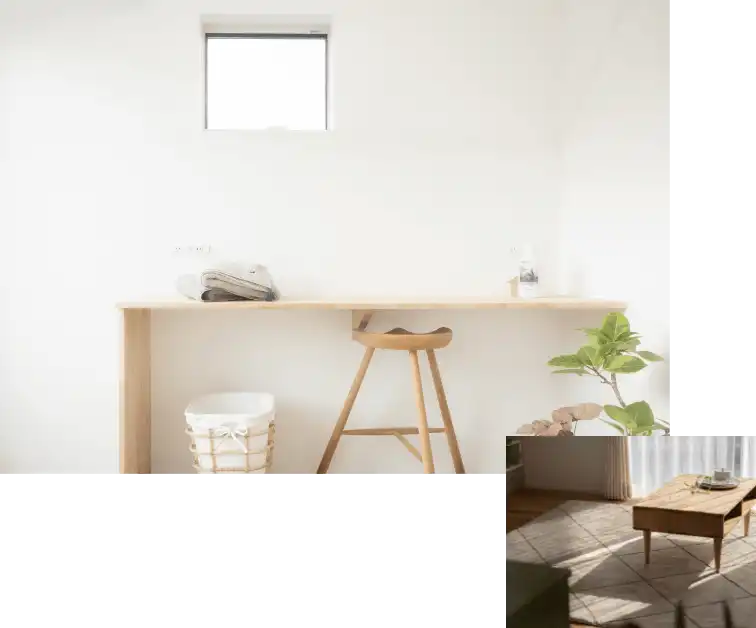


03
良いものを
適切な価格で
快適に安全に暮らせる品質の高い住まいと、
お客様のゆとりある生活を両立するために。
予算に合わせて、最大限夢をかなえる
お手伝いをさせていただきます。


わたしたちが大切にしていること、
それはそこに住まう人の人生が
豊かになること。
About Us わたしたちの家づくり
ご相談からアフターフォローまで
お客様に寄り添います
アップルハウスで建築に携わるのは、国家資格を持つ建築士。
洗練されたデザインでありながら、安全性と機能性を追求した住まいづくりをご提案します。
わたしたちは、お客様の快適な暮らしを末永く叶えるために、施工からアフターフォローまでを支える、お客様の生涯のパートナーとなることを目指しております。
Plan さまざまな家づくりのかたち
予算やご要望に合わせて
プランをご用意しております
自由設計の「cocochi~ここち~」と、規格住宅の「YOHAKU-余白-」をご用意。
お客様のご事情に合わせて家づくりをご提案いたします。
リフォーム対応も行っているため、経年劣化やライフスタイルの変化でお悩みの方は、 ぜひご相談ください。 More
フルオーダーでつくる
心地よい空間
フルオーダー・セミオーダーでつくるこだわりの住宅。
お客様のライフスタイルやお好みをもとに、
予算のやりくりも含めて建築士と相談を重ねながら、
オンリーワンの住宅をご提案します。
あなた色に染められる
規格住宅
あなた色に染められる余白を残した規格住宅。
四角形だけでなく、平屋、コの字型、L字型まで、
土地の形やお好みに合ったプランから理想の住宅を組み立てられます。
いつまでも
豊かに過ごせる住空間を
アップルハウスではリフォームも対応しております。
マイナートラブルなどによる小さな改修から、
間取りの変更のような大きな改修まで作業が可能です。
Case 施工事例・お客様の声
Info 新着情報
Knowledge 家づくり基礎知識
失敗しない家づくりのために。
設計のことや土地選びのこと、お金のこと。家づくりに はさまざまな不安が付きものです。失敗しない家づくりのために、注文住宅を建てるうえで考えておくべきポイントや、資金計画などについておさえておきましょう。

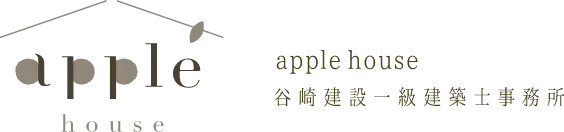
- 会社名
- 株式会社谷崎建設一級建築士事務所
- 所在地
- 〒771-1272
徳島県板野郡藍住町勝瑞成長141-23
- TEL
-
フリーダイヤル:0120-378-678
TEL 088-641-1771(代)
- 営業時間
- 9:00−18:00 日曜・祝日定休